✨歴史に詳しくないあなたも楽しめる!✨
こんにちは!歴史の扉へようこそ。
織田信長がこの世を去り、天下が再び乱れ始めた激動の時代。そんな中で、一歩一歩着実に力をつけ、やがて豊臣秀吉に次ぐ実力者へと成長した人物がいました。そう、徳川家康です。
しかし、家康は信長亡き後、すぐに天下を獲りにはいきませんでした。不思議ですよね?なぜ彼は、当時破竹の勢いだった秀吉のもとで「No.2」の道を選んだのでしょうか?
この記事では、歴史にあまり詳しくない方にも心に語りかけるような丁寧な言葉で、豊臣政権下で家康がどのように力を蓄え、最終的に天下人へと駆け上がっていったのか、その巧みな戦略と処世術を分かりやすくご紹介します。
家康の「待つ」という着実な歩みを知ることは、現代を生きる私たちにとっても、実力をつけた者が次にどう動くべきか、人生の大きなヒントとなるかもしれません。さあ、一緒に家康の天下取りへの道のりを辿ってみましょう!
互角の実力!徳川家康と豊臣秀吉の「小牧・長久手の戦い」とその後の賢明な判断
家康がその力を世に知らしめた最初の大きな出来事、それが天正12年(1584年)に勃発した「小牧・長久手の戦い」でした。この戦いで、家康は当時まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった豊臣秀吉の大軍を相手に、互角以上に渡り合い、その並外れた武威と、彼に命を捧げる家臣たちの固い結束力を天下に知らしめました。
もし、これが戦国時代の初期であれば、どちらかの勢力が滅びるまで戦いは止まらなかったかもしれません。しかし、長きにわたる戦乱によって、世の中全体が疲弊しきっていた時代。家康もまた、ここで大きな決断を迫られることになります。
なぜ戦いをやめたのか?家康の「現実」を見据えた判断
実は当時、家康の領国は地震や大雨といった大規模な天災に見舞われ、財政的に非常に苦しい状況にありました。田畑は荒れ果て、これ以上大規模な戦いを続けるだけの体力は残されていなかったのです。
一方で、秀吉は桁外れの経済力と、圧倒的な兵の動員力を誇っていました。個々の戦術では勝てても、国力を含めた総力戦ではいずれ不利になる。家康は、この現実を冷静に見極めていたのでしょう。
「戦って勝てない相手ではない。しかし、その先に待っているのは、さらなる混乱と疲弊しきった領国かもしれない…。」家康の脳裏には、彼が若き日に掲げた旗印、「厭離穢土、欣求浄土(おんりえど、ごんぐじょうど)」、すなわち「汚れたこの世を厭い離れ、平和な安らかな世界(浄土)を心から求める」という誓いの言葉が強くよぎったのかもしれませんね。
こうした深い思慮の末、家康は秀吉に臣従する道を選びます。これは決して、戦に敗れたからという単純なものではなく、未来を見据えた、非常に戦略的な選択だったのです。この決断が、後の天下取りへの第一歩となりました。
No.2としての生存戦略!豊臣政権下での徳川家康の巧みな立ち回り
家康の臣従を受け入れた秀吉もまた、家康の並外れた実力と影響力を高く評価していました。秀吉は家康を力ずくで押さえつけるのではなく、「味方」として政権の中枢に取り込むことで、自らの天下をより盤石にしようと考えたのです。
家康は秀吉の期待に応え、豊臣政権の重鎮として、その役割を全うします。
- 天正14年(1586年):朝廷から正三位(しょうさんみ)に叙任され、本拠地を交通の要衝である駿府城へと移します。これは、秀吉が家康を重く用い、主要な位置に置く意図があったとされます。
- 天正15年(1587年):さらに位階を上げ、従二位(じゅにい)・権大納言(ごんだいなごん)に昇進。そして、関東や奥羽(東北地方)の監視役という、非常に重要な役割を任されました。これは、秀吉が家康の力を信頼し、東日本の統治を委ねる姿勢の表れでもありました。
家康は、関東の雄である北条氏に秀吉への恭順を促すなど、豊臣政権の安定に寄与することで、いわば「Win-Win」の関係を築こうとしました。(残念ながら、北条氏はこれに抵抗し、最終的に滅亡してしまいますが…)
250万石への大出世!「関東移封」の真意とは?
天正18年(1590年)、秀吉による小田原征伐で北条氏が滅亡すると、秀吉は家康に一つの大きな命令を下します。それが「関東移封(かんとういほう)」です。
これは、家康が代々治めてきた駿河、遠江、三河、甲斐、信濃の5か国から、新たに武蔵、伊豆、相模、上野、上総、下総など、広大な関東8か国へ領地を移すというものでした。この移封により、家康の石高(土地の生産力を示す単位)は、それまでの120万石から、なんと一気に250万石へと倍増したのです!
この「関東移封」については、さまざまな見方があります。
「秀吉が家康を豊臣家の本拠地である中央から遠ざけ、まだ統治が不安定な東国で家康の力を削ごうとした」という解釈も確かに存在します。しかし、別の見方をすれば、これは秀吉が家康をそれほどまでに信頼し、重要視していた証とも言えます。
当時の関東は、まさに日本の新しい中心地となりうる広大な平野を抱え、東国の要衝として非常に重要な地域でした。秀吉は、この東国の抑えという重大な役割を、誰よりも信頼できる家康に託したのではないでしょうか。家康は、秀吉にとってそれほどまでに「重み」のある、代えのきかない存在だったのです。
国力を温存できた「朝鮮出兵」
文禄元年(1592年)に始まった秀吉の「朝鮮出兵」は、多くの西国大名たちに甚大な負担を強いました。兵力だけでなく、食料や物資の調達、そして長期にわたる海外での戦いは、各藩の財政を大きく圧迫しました。
しかし、幸いなことに、家康をはじめとする関東・東北の大名は、出兵の拠点である九州の名護屋城まで軍を進めたものの、実際に朝鮮半島へ渡ることはありませんでした。これにより、西国大名が疲弊していくのを横目に、家康は自らの国力を温存することに成功します。これもまた、結果的に家康の天下取りを後押しする、重要な要因の一つとなりました。

引用元: 加治まや (@maya_kaji) 2021年7月6日のツイートより
当時の名護屋城は、単なる兵の集結地ではありませんでした。全国から集まった大名や商人によって、巨大な城下町が形成されるほどの一大拠点だったのです。この大規模な事業に参加しながらも、最前線での消耗を免れた家康の立ち位置は、非常に幸運だったと言えるでしょう。
豊臣家の弱体化を招いた「豊臣秀次事件」
文禄4年(1595年)、豊臣政権を根底から揺るがす大事件が起こります。秀吉が、自身の後継者として関白の位に就けていた甥の豊臣秀次(とよとみひでつぐ)に謀反の疑いをかけ、高野山へ追放。ついには切腹を命じ、その妻子や家臣たちまでも処刑した「豊臣秀次事件」です。
一般的には、この事件の2年前に側室の淀殿との間に待望の実子・秀頼(ひでより)が生まれたことで、将来の争いの種を摘むために秀次を排除した、と言われています。しかし、この秀吉の非情な決断が、結果的に豊臣政権の命取りとなりました。
もし秀次が生きていれば、幼い秀頼が成長するまでの間、秀次が政権を担い、豊臣家は安泰だったかもしれません。たとえ将来、秀頼と秀次が対立したとしても、それは豊臣家内部の問題として収まっていた可能性が高いでしょう。しかし、秀吉は自らの手で後継者の選択肢を断ち切ってしまったのです。これにより、豊臣家に何かあった場合、頼れるのは家康しかいないという、極めて危険な状況が生まれてしまいました。

引用元: HISTRIP|古き良き日本の魅力旅を発信中!! (@HISTRIP_JPN) 2021年7月4日のツイートより
当時の秀次が、近江八幡の城下町を発展させるなど、優れた為政者としての一面を持っていたことは、あまり知られていません。彼のような有能な人材を失ったことは、豊臣家にとってあまりにも大きな損失だったと言えるでしょう。
ついにその時が来た!秀吉死後、天下への布石
慶長3年(1598年)、天下人・豊臣秀吉が病に倒れ、その波乱に満ちた生涯を閉じます。死の直前、秀吉はまだ幼い実子・秀頼の将来を深く案じ、有力な大名たちによる「五大老(ごたいろう)」と、政権の実務を担う「五奉行(ごぶぎょう)」という制度を定め、彼らに秀頼の後見を託しました。
機能しなかった「五大老・五奉行制度」
五大老には、徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家という、まさに日本の有力大名が顔を揃えていました。秀吉は、彼らが互いに牽制し合うことで、権力のバランスが保たれると考えたのでしょう。
しかし、これは秀吉の「気休め」に過ぎませんでした。各大名の石高を見てみると、その力の差は歴然です。
- 徳川家康:250万石
- 毛利輝元:120万石
- 上杉景勝:120万石
- 前田利家:83万石
- 宇喜多秀家:57万石
家康の石高は、他の4人の大老を合計した石高に匹敵するほど突出していたのです。この圧倒的な実力差の前では、秀吉が定めた制度も、もはや形骸化するしかありませんでした。
着々と影響力を強める家康
秀吉の死後、家康は五大老の筆頭として、天下の差配(さはい:物事を取り仕切ること)を始めます。秀吉が生前、大名同士の勝手な行動を禁じていたにもかかわらず、家康は有力大名同士の私的な婚姻を推し進めるなど、巧みに味方を増やし、その影響力を着々と強めていきました。
もちろん、石田三成をはじめとする五奉行たちは「秀吉様の遺言に背くものだ!」と猛反発します。しかし家康は、表向きは幼い秀頼公を敬い、礼を尽くす姿勢を崩しません。「すべては豊臣家のため」という大義名分を掲げながら、水面下で着々と自分の思う通りに事を進めていくのです。
家康は、決して焦らずとも、やがて時が来れば自然と天下は自分の元に転がり込んでくると確信していたのかもしれません。そして、その思惑通りに時代は大きく動いていきます。

引用元: DOLLY℗ ドリー (@dollyfunklove) 2021年7月5日のツイートより
この大阪城こそ、秀頼が座する豊臣政権の中心地。しかし、その権威も、家康の巨大な実力の前では、徐々に影が薄くなっていくのでした。
天下分け目の決戦!「関ヶ原の戦い」へ
慶長5年(1600年)、ついに歴史が大きく動きます。家康は、五大老の一人である会津の上杉景勝(うえすぎかげかつ)に謀反の疑いがあるとして、諸大名を率いて会津征伐へと向かいます。これはあくまで、豊臣家の名のもとに行われる公式な出兵という形がとられました。
家康を追い詰めた石田三成の策
家康が江戸に到着した頃、この隙を突いて、五奉行の石田三成(いしだみつなり)が毛利輝元を総大将に担ぎ上げ、「打倒家康」の兵を挙げます。これは、家康を東国へおびき出し、その留守の間に西国で挙兵するという、三成と上杉家の軍師・直江兼続(なおえかねつぐ)が仕組んだ、まさに壮大な作戦だったと言われています。
三成の思惑通り、家康は東西から挟み撃ちにされるという絶体絶命の危機に陥りました。しかし、三成には大きな誤算がありました。
なぜ豊臣恩顧(おんこ)の大名は家康についたのか?
三成の最大の誤算は、秀吉に恩を受けたはずの「豊臣恩顧」の大名たちが、皮肉にもこぞって家康側についてしまったことです。加藤清正や福島正則といった武断派(軍事力を重んじる派)の大名たちは、かねてから文治派(行政能力を重んじる派)の三成と対立しており、彼に従うことを良しとしませんでした。
人望の面で三成に勝る家康の周りには、自然と多くの大名や武将たちが集まったのです。それだけ家康の度量(器の大きさ)や包容力が大きかった証拠とも言えるでしょう。
こうして会津へ向かっていた討伐軍は、急遽方向転換して西へ。家康率いる「東軍」と、三成率いる「西軍」による、日本史上最大の天下分け目の決戦「関ヶ原の戦い」の火蓋が切って落とされたのです。
戦いの実態は「豊臣家中の内乱」だった
この戦いは、よく「豊臣家 対 徳川家」の戦いと見られがちですが、その実態は少し違います。東軍の総大将は徳川家康、西軍の総大将は毛利輝元と、どちらも豊臣家の五大老でした。つまり、これは厳密には「豊臣政権内部の勢力争い(内乱)」だったのです。
そのため、豊臣家の当主である豊臣秀頼やその母・淀殿は、どちらの勢力にも味方せず、静観の構えをとりました。これが三成にとっては、さらなる誤算となります。もし「秀頼公は西軍にあり!」というお墨付きがあれば、戦況は大きく変わっていたかもしれません。
戦いは当初、地の利を得た西軍が優勢に進めました。しかし、戦いの趨勢(すうせい:成り行き)を見守っていた小早川秀秋(こばやかわひであき)が、突如として西軍を裏切り、東軍に寝返ったことで、勝敗は一瞬にして決しました。

引用元: 岐阜お城研究会代表 (@shirosukiGifu) 2021年7月5日のツイートより
小早川秀秋が陣を敷いた松尾山は、関ヶ原の戦場全体をまさに一望できる絶好の場所でした。彼の一挙手一投足が、戦いの行方を左右する重要なカギを握っていたのです。
この劇的な勝利により、家康は事実上の天下人としての地位を確立しました。豊臣家は領地を失うことはありませんでしたが、その権威は大きく失墜し、日本は徳川家康を中心とする新たな時代へと突入していくことになります。
まとめ:徳川家康の天下取りに学ぶ「待つこと」の重要性
今回は、大大名となってからの徳川家康が、豊臣政権下でどのように立ち回り、最終的に天下を手にしたのかを見てきました。
家康の行動は、一貫して「慎重」そのものでした。彼は決して焦ることなく、No.2という立場に甘んじながらも、来るべき時に備えて着実に力を蓄え、ライバルたちが自滅していくのを冷静に待ち、機が熟すのをじっと待ったのです。
関ヶ原の戦いでは、石田三成の策にはまり、危うい場面もありました。しかし、それまでに彼が築き上げてきた「人望」と「信頼」が、最終的に彼を勝利へと導きました。
すぐに結果を求めがちな現代社会ですが、時には家康のように、じっと耐え忍び、広い視野で大局を見て行動することの重要性を、彼の生き様は私たちに教えてくれているのかもしれませんね。
もっと戦国時代や歴史の英雄について知りたい方へ
戦国時代の魅力的な人物はまだまだたくさんいます。他の武将たちの活躍もぜひご覧ください。


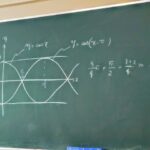
コメント