1970年11月25日、作家・三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自決を遂げた事件は、「三島事件」として戦後日本に深い刻印を残しました。文学、政治、軍事、そして日本人の精神性に深く関わるこの出来事は、50年以上が経過した今なお、多くの議論を呼び続けています。特に、2025年は三島由紀夫の生誕100年という記念すべき年にあたります。
三島由紀夫事件の全貌:市ヶ谷駐屯地での衝撃的な出来事
まずは、1970年11月25日に市ヶ谷駐屯地で何が起きたのか、その一連の流れを確認していきましょう。
自衛隊幹部への面会から人質事件、そして衝撃の演説へ
事件当日の午前11時ごろ、三島由紀夫は自らが組織した民間防衛組織「盾の会」のメンバー4人(森田必勝、小賀正義、古賀浩靖、岡本定)とともに、東京都新宿区にある陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪れました。彼らは、親交のあった東部方面総監・益田兼利陸将に面会を求め、スムーズに総監室へと案内されます。
しかし、面会が始まって間もなく、予期せぬ事態が起こります。三島たちは突如として益田総監を拘束し、総監室をバリケードで封鎖。これにより、事実上の人質事件へと発展してしまいました。三島は、駐屯地の自衛官約1,000名を本館前に集合させ、自身が演説を行うこと、盾の会メンバーの立ち会いを許可すること、そして約2時間の間、妨害しないことなどを要求しました。事件の報を受けて、現場には警察官、報道陣、そして機動隊が続々と集結し、駐屯地はかつてないほどの緊張感に包まれました。
この間、益田総監は一時的に命の危険にさらされ、総監室では盾の会メンバーと自衛隊側の間で物理的な小競り合いも発生するなど、緊迫した状況が続いていました。
バルコニーからの「檄」、そして割腹自決へ
正午過ぎ、三島はついに本館のバルコニーに現れ、集まった約1,000名の自衛官に向けて演説を行います。その内容は、日本国憲法第9条によって「骨抜きにされている」と彼が考えていた自衛隊の現状を厳しく批判し、憲法改正による「真の自衛隊の成立」を強く訴えるものでした。しかし、多くの隊員からは三島に対する怒号が飛び交い、報道ヘリコプターの騒音も重なり、残念ながらその声は多くの隊員に届きませんでした。
約10分間の演説を終えた三島は、総監室へと戻ります。そして、室内の赤い絨毯の上に正座し、短刀で自らの腹部を切り裂く「割腹自決」に及んだのです。介錯(切腹を助ける行為)を試みたのは、盾の会の森田必勝でしたが、数度の失敗の末、別のメンバーである古賀浩靖が介錯を務めました。その後、森田もまた三島の隣で自決し、古賀が介錯を施しました。この二人の死は、単なる過激な行動として片付けられない、彼らの思想と行動が一体となった強烈なメッセージとして、後世に大きな衝撃を与えることになります。
三島由紀夫が事件を通して訴えたかったこと:『檄』と辞世の句に込められた思想
三島由紀夫はなぜ、このような壮絶な死を選んだのでしょうか。その背景には、彼の深く、そして複雑な思想がありました。
『檄』に凝縮された国家と自衛隊への「怒り」と「問い」
事件当日、三島由紀夫が市ヶ谷駐屯地で撒布した文書「檄(げき)」には、自衛隊と国家のあり方に対する彼の切実な問いと、激しい怒りが綴られていました。その主張は、以下のように要約することができます。
- 自衛隊の「矛盾」の指摘: 憲法によって武力不保持を謳われながらも、実際には武装している自衛隊は、「違憲」という矛盾を抱えた存在である。
- 自立性の喪失: 自衛隊は政治家によって人事や財政を支配され、本来あるべき「国体を守る」という自立性が失われている。
- 憲法擁護への疑問: 本来、国の根本を守るべき自衛隊が、皮肉にもその国体を否定しかねない現行憲法を「擁護」している。
- 警察力への過信: 国家秩序を警察力だけで維持できるという幻想に陥っている日本の現状への警鐘。
三島は、自衛隊が「魂なき存在」と化すことを何よりも恐れていました。彼は、たとえ命を賭してでも、日本の伝統と精神性、そして天皇を中心とした「国体」を守るべきだと強く訴えかけました。最終的に、「生命尊重だけでは国家を守れない。日本の精神を守る真の軍隊を作るべきだ」という結論に至り、その思想を体現するために行動を起こしたのです。
1970年昭和45年11月25日に
作家の三島由紀夫(本名・平岡公威)
が、憲法改正(憲法第9条破棄)
のため自衛隊に決起(クーデター)
を呼びかけた後に割腹自殺をした
事件である。三島が隊長を務める
「楯の会」のメンバーも事件に
参加したことから、その団体の名前
をとって楯の会事件とも呼ばれる… pic.twitter.com/XEZGK8t0GR— 🎌不動心🎌 ✨Neo✨ (@tenkataihei369) June 2, 2025
辞世の句に込められた武士としての覚悟と美学
三島由紀夫が事件直前に残した辞世の句、「益荒男(ますらお)が たばさむ太刀の 鞘鳴り(さやなり)に 幾世(いくよ)へぬる 大和(やまと)心か」には、彼が生涯をかけて追求した武士道精神と、日本人としての覚悟、そして独特の美学が凝縮されています。この句は、刀が鞘に収まっている状態でもその存在を主張する「鞘鳴り」に、日本の武士道精神がどれほどの時を経て受け継がれてきたのかという、三島自身の問いかけと決意が込められています。
また、三島とともに自決した森田必勝の辞世の句もまた、その決意と共鳴する内容であり、彼らの行動が単なる衝動的なものではなく、深い思想と覚悟に裏打ちされたものであったことを示しています。彼らの死は、言葉による思想の表明に留まらず、自らの肉体と命を賭して思想を体現する、一種の「精神的パフォーマンス」とも解釈できるでしょう。日本の伝統、武士道、天皇、国体――これらの概念を一身に背負いながら、「生きて思想を叫ぶ」ことよりも、「死をもって思想を体現する」ことを選んだ三島由紀夫の行動は、世界の文学史においても類例のない、極めて特異なものでした。
三島事件が社会に与えた影響と、その後の評価の変遷
三島事件は、当時の日本社会に大きな衝撃を与え、様々な影響をもたらしました。その評価は、時間とともに変化し続けています。
益田総監の辞任と政治の関与、そして盾の会メンバーの裁判
この事件の責任を取り、益田兼利陸将は辞職を余儀なくされました。後に語られるエピソードとして、当時の防衛庁長官であった中曽根康弘氏が「君はもう将官としての地位を極めた。私には将来がある」と語り、辞任を促したとされます。この出来事は、軍隊(自衛隊)と政治の関係性、そして政治が軍をどのように扱うかを示す一幕として、歴史に刻まれています。
事件後、生き残った「盾の会」のメンバーたちは警察に拘束され、裁判にかけられました。最終的に、彼らには4年の実刑判決が下されました。彼らの行動は、法的には反社会的行為と見なされましたが、その動機の純粋さや、三島由紀夫の思想に殉じようとした精神性の高さは、一部では評価される声もあり、裁判結果に対して「重すぎる」という意見も存在しました。
事件への世間の反応と、再評価の動き
事件当時、日本のマスコミや多くの知識人からは、三島の行動は「暴挙」「常軌を逸した行動」として厳しく断罪されました。しかし、時代が進むにつれ、三島由紀夫が事件を通して訴えようとした思想の本質を冷静に評価しようとする動きが強まっています。文学者としての三島由紀夫の国際的な名声とは別に、政治的思想家・行動者としての彼の評価も、近年になって再検討されつつあります。彼の著作や行動が、現代社会の問題と結びつけて論じられることも増えてきました。
現代に生きる三島由紀夫の「問いかけ」:国家と精神のあり方
三島由紀夫が投げかけた問いは、50年以上が経った今もなお、私たち日本人にとって重要な意味を持ち続けています。
国家とは何か?軍隊とは何のために存在するのか?
三島由紀夫の根底にあった訴えは、突き詰めれば「日本は日本であり続けるべきか?」という問いに収束します。グローバル化が進み、経済優先の社会が加速し、そして憲法改正の議論が再び活発になる現代において、三島由紀夫が発した問いかけは決して過去のものではありません。私たちは今一度、自分たちの国や社会のあり方、そして自衛隊の存在意義について深く考える必要があるのではないでしょうか。
彼の行動を単に「過激な思想家の末路」として片付けてしまうのは簡単です。しかし、その背後には、現代社会における政治のあり方と、日本人の精神性の乖離に対する、痛烈な問題提起が含まれています。三島由紀夫は、現代の日本人が忘れかけている「誇り」や「伝統」といった精神的な価値の重要性を、命を賭して示そうとしたのかもしれません。
行動と思想の一致という「美学」
三島由紀夫の行動は、多くの人々にとって理解しがたい、あるいは衝撃的なものであったかもしれません。しかし、彼は単に言葉で思想を語るだけでなく、自らの命を懸けてその思想を体現したという点において、現代の政治家や評論家にはなかなか見られない、徹底した一貫性を持っていました。彼の行動は、まさに「文武両道」を極めた三島由紀夫ならではの、「行動する美学」だったとも言えるでしょう。
2025年、三島由紀夫の生誕100年という節目に立つ今だからこそ、私たちは彼の残した言葉と行動を、感情論に流されることなく、より冷静かつ誠実に読み解き直すべき時期に来ているのではないでしょうか。
まとめ:三島由紀夫事件の再評価と現代への示唆
三島由紀夫事件は、単なる政治テロや暴挙としてだけではなく、彼が遺した深い思想、そしてそれを支えた文学と武士道精神の融合が凝縮された出来事として、多角的に捉えられるべきものです。この事件は、現代日本にとって無視できない重要なメッセージを含んでいます。
日本国憲法、安全保障、自衛隊の存在意義、そして日本人の精神文化――。これらの根源的なテーマを改めて深く考える機会として、三島由紀夫事件は今後も語り継がれていくことでしょう。本記事が、三島由紀夫の思想と行動について、皆さんが深く考察するきっかけとなれば幸いです。

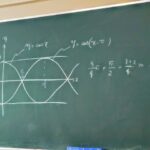

コメント